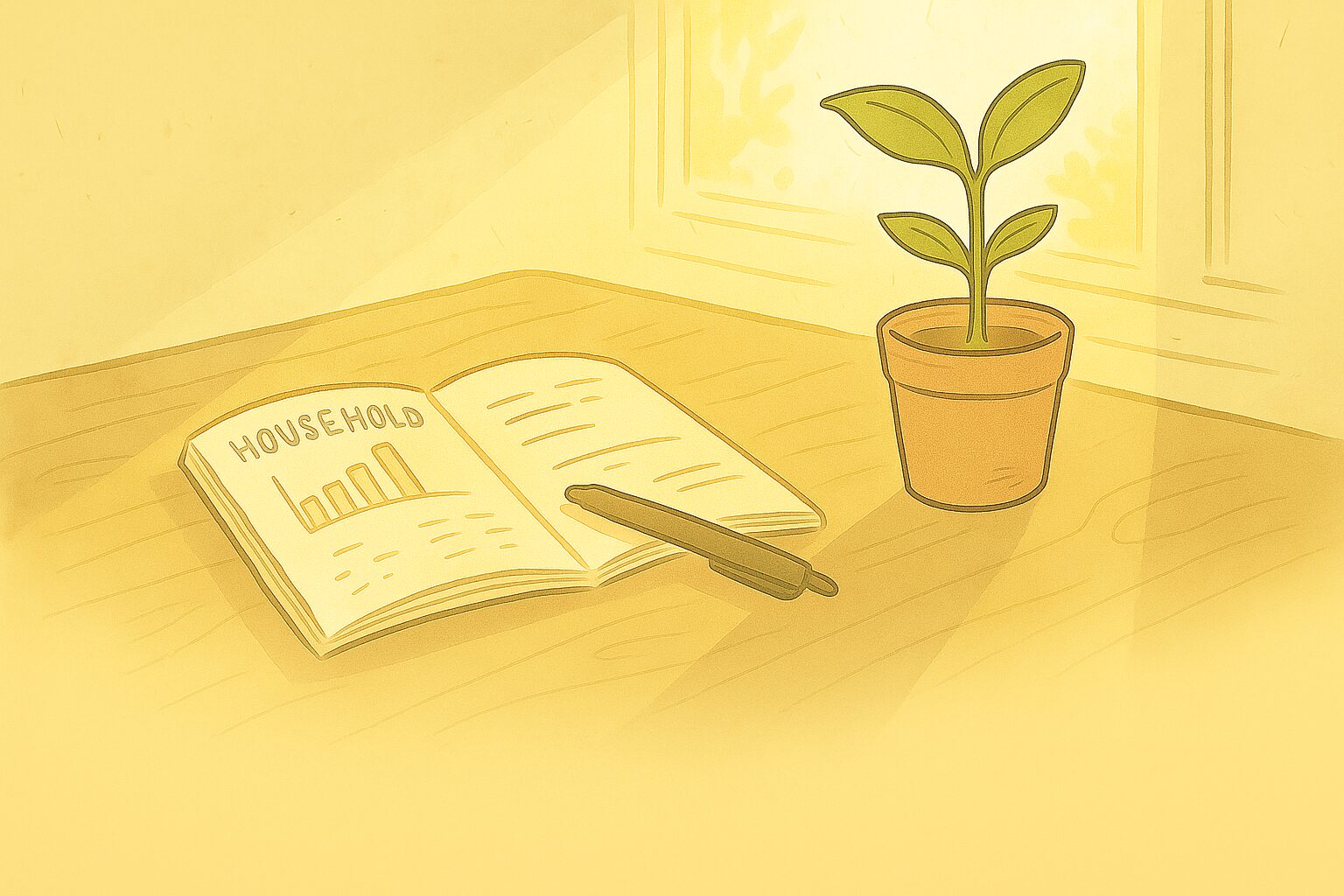こんにちは、ごんです。
突然ですが、皆さんは「公務員」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?
- 安定していそう
- 毎日、定時で帰れそう
- 仕事が楽そう…
もしかしたら、そんなイメージをお持ちの方も多いかもしれませんね。
公務員になって10年近くになる私も、かつてはそう思っていました。
その安定を求めて公務員になった、休職経験もある、ごく普通の現役職員です。
今回は、そんな私が日々の中で感じている、公務員の仕事のリアルな「光」と「影」について、正直にお話ししたいと思います。 皆さんが抱くイメージは、半分は合っていて、半分は少し違うかもしれません。
この記事が、公務員という仕事をより深く知るための、一つの「よりみち」になれたら嬉しいです。
私が感じる「公務員のやりがい」(光の部分)

「ありがとう」より嬉しい、確かな手応え
正直に言うと、私は市民の方から直接「ありがとう」と言われた経験よりも、クレームや理不尽な要求を受けた時の、嫌な記憶の方が鮮明に残ってしまうタイプです。 そして、数年前まで「もうこの仕事は辞めたい」と毎日思いながら働いていた時期もありました。
「公務員のやりがい」と聞かれると、今でも少し言葉に詰まってしまいます。
でも、そんな私が、「この仕事をしていて良かったな」と心から思えた瞬間が、実は日々の業務の中ではなく、プライベートな場面で何度かありました。
身近な人を、「知識」で助けられた経験
それは、自分の持っている行政の知識や制度の理解が、身近で大切な人たちの助けになった時です。
例えば、親戚が亡くなった際には、煩雑な行政手続き(死亡届、戸籍関係など)をスムーズに進める手助けができました。 友人の子育てに関する制度の質問に答えられたり、水道トラブルの際に、市がホームページで紹介している指定業者の一覧を教えたりした時には、「そんなのがあるんだ!」と驚き、感謝されました。
特に印象に残っているのは、祖母が骨折し、介護認定を受ける必要が出た時のことです。 私の親は「まずは骨折が少し落ち着いてから申請しよう」と考えていましたが、それでは認定が受けられない可能性があることを、私は仕事の知識で知っていました。「今すぐに動こう」とアドバイスし、無事に手続きを進めることができたのです。
地味だけど、これが私の「やりがい」
これらの経験は、決して派手なものではありません。誰かから表彰されるわけでも、大きな達成感が得られるわけでもない。 でも、自分が日々向き合っている地味な知識や手続きが、いざという時に、大切な家族や友人の人生を具体的に支える力になる。そのことを実感できた時、「ああ、この仕事にも、確かな価値があるのかもしれないな」と、少しだけ自分の仕事に前向きな気持ちになれるのです。
華やかさはないけれど、誰かの日常に、そっと寄り添い、支えることができる。 それが、私が感じている、公務員の仕事の「やりがい」の一つです。
もちろん、それだけじゃない。「公務員の大変さ」(影の部分)

民間企業とは違う、公務員ならではの「大変さ」
「やりがい」についてお話ししましたが、もちろん、それだけでは語れない「大変さ」もたくさんあります。
「公務員は安定していていいね」とよく言われます。
確かに、仕事がなくなる心配が少ないという意味では、その通りかもしれません。
でも、民間企業とは目的が根本的に違うからこその、特有の難しさがあると私は感じています。
民間企業は「利益」を追求しますが、私たちは「全体の奉仕者」として、利益とは別の目的のために働いています。 時には話がなかなか通じない方にも、公平に対応しなければならない。
お給料は、市民の皆さんが納めてくれた「税金」からいただいている。この事実が、時には大きなプレッシャーとしてのしかかってくることもあります。 (民間の方から見れば「ぬるま湯だよ」と思われるかもしれませんが、そこには目に見えにくい、精神的な大変さがあると感じています。)
その上で、私が特に「大変だな」と感じてきたことを、いくつかご紹介します。
① 数年ごとの「転職」? 異動の多さと専門性の悩み
まず、公務員特有の悩みとして「異動の多さ」があります。 数年ごとに、全く畑違いの部署へ移ることは珍しくありません。本当に、転職するくらいの大きな変化です。前にいた部署で培った法律の知識や仕事の進め方が、次の部署では全く役に立たない、なんてことはザラにあります。 法律に則って厳密に業務を進める部署もあれば、窓口での対人対応がメインの部署もある。その度に、ゼロから新しいことを学び直さなければなりません。
② 暴言、そして時には…理不尽な要求との戦い
これは民間企業でも同じかもしれませんが、公務員の仕事は、市民の方々からの理不尽な要求や、時には暴言、そして残念ながら暴力といったものに晒される機会も少なくありません。
全体の奉仕者として、どんな相手にも誠実に対応しなければならない。そう頭では分かっていても、心をすり減らしてしまうことは、正直に言って、たくさんあります。
③ いまだに残る「紙文化」と、非効率な業務
そして、日々の業務で感じるのが、徹底した「紙文化」と、それに伴う非効率さです。
重要な決定は、全て紙の書類にハンコをもらう「決裁」という手続きが必要で、そのために上司の席まで直接足を運ばなければなりません。
インターネット環境も、皆さんがご家庭で使っているような快適なものではなく、調べ物一つするにも時間がかかります。(個人的には、Macが使いたくてたまりません!) 「この会議、本当に必要かな…?」と感じるような、無駄に思える会議が多いのも事実です。
④ 白黒つけたい自分と、「全体の奉仕者」としての立場
最後に、これは私の性格も影響していますが、「全体の奉仕者」であることの精神的なプレッシャーです。
個人的には「こうすべきだ」という白黒はっきりした意見を持っていても、公務員という立場上、様々な方の意見を尊重し、公平に対応しなければなりません。そのため、時には自分の本心を抑え、話をはぐらかすような、曖昧な言い回しをせざるを得ない場面もあります。
それが、白黒つけたい性格の私にとってはすごく嫌で、大きな葛藤を感じる部分でもあります。
それでも私が「公務員」を続ける、たった一つの理由
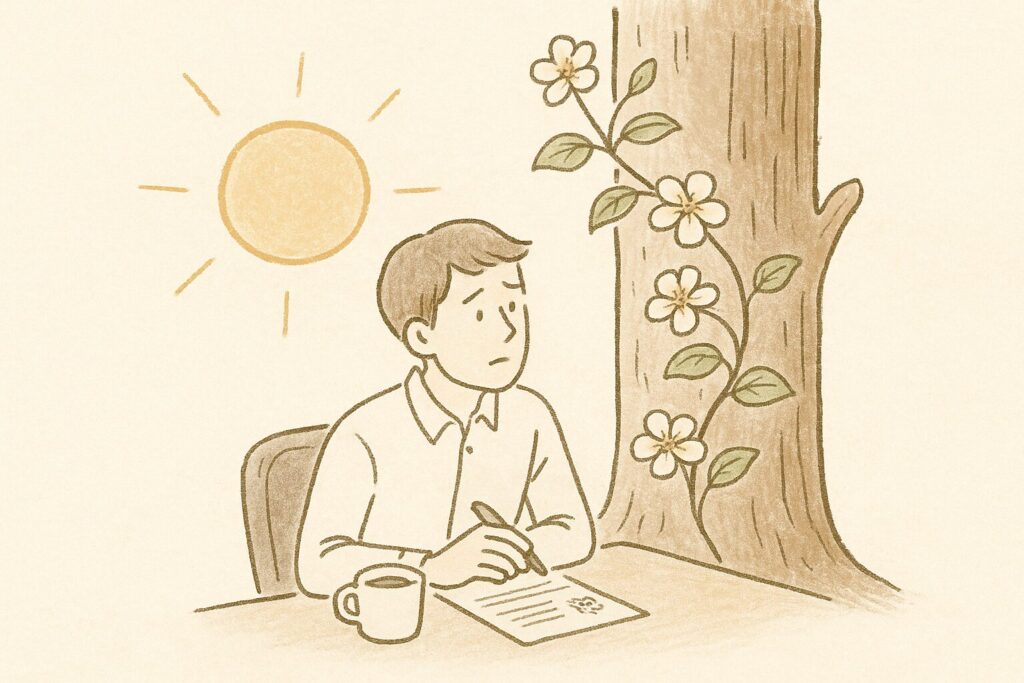
ここまで、公務員の仕事の「やりがい(光)」と「大変さ(影)」について、私の経験から正直にお話ししてきました。 では、そんな私が、なぜ今も公務員を続けているのか。
正直に言うと、自分でもはっきりと「これだ!」という答えは、まだ見つかっていません。
大きなやりがいを感じているわけでも、心から「この仕事がやりたい」と燃えているわけでもない。むしろ、「この働き方で、精神的にも肉体的にも、この先ずっとやっていけるのだろうか」という不安を抱えながら働いている、というのが本音です。
ただ、一つだけ確かな理由があります。
「安定という基盤があるからこそ、新しい挑戦もできる」ということです。
毎月の生活が保障されているという安心感があるからこそ、私はこうして自分の内面と向き合ったり、新しいスキルを学んだり、誰かの役に立つかもしれない発信をしたりする、そんな「よりみち」をする心の余裕が生まれています。
仕事に全てを捧げるのではなく、仕事はあくまで生活の土台と捉え、そこから得たエネルギーで、自分の人生を豊かにしていく。そんな働き方があっても良いのではないかと、今は思っています。(もちろん、その考え方自体にも、まだ葛藤はありますが…)
まとめ:公務員という「人生のよりみち」
公務員の仕事は、外から見えるイメージだけでは分からない、非常に多様で、人間味あふれる世界です。そして、決して「楽な仕事」ではない、ということも、この記事を通して少しでも伝わっていたら嬉しいです。
最後に、これから公務員を目指す人、そして今まさに公務員として悩んでいる人へ。 この記事が、あなたのキャリアを考える上での、一つの「よりみち」のきっかけになれたなら、これほど嬉しいことはありません。
私がお伝えできるのは公務員という部分ですが、どんな道を選んでも、きっと大変なことはあります。
その中で自分なりの「やりがい」や「続ける理由」を見つけたり、あるいは私のように、そこを基盤に新しい「よりみち」を始めたりすることもできるはずです。
あなたの人生の選択が、素敵なものでありますように。
以上、ごんでした