公務員試験に挑むあなたへ。
「範囲が広すぎて、どこから手をつければ…」
「今の勉強法で、本当に大丈夫なのかな?」
——かつての私も、同じ不安を抱えていました。
一度は完全にドロップアウトした私が、どうやって再び立ち上がり、合格を掴み取ったのか。この記事は、その「ちょっとリアルな体験談」です。
私のスタートラインは、こんな感じでした。
- 法律や経済の知識は完全にゼロ
- 大学2年で受けた公務員講座を、半年で挫折した経験あり
- 周りの熱量についていけず、「まだ大丈夫」と高をくくっていた
もし、少しでも「自分と似てるかも」と感じてくれたなら、きっとこの記事があなたの長い受験勉強の道のりを照らす、小さな光になるはずです。
では、私の七転八倒の物語、本題に入っていきましょう。
【第1章】回り道と決意。筆記試験・逆転の始まり

挫折。何もできないまま卒業
すべての始まりは、大学2年生の時に受けた公務員講座でした。
「周りより早く準備をすれば、きっと有利になるだろう」
——そんな軽い気持ちで、私はその扉を叩いたのです。
しかし、そこで私を待っていたのは、想像を絶する現実でした。
テキストを開けば、憲法、民法、行政法、ミクロ経済、マクロ経済…と、これまで全く触れたことのない単語のオンパレード。
真剣な眼差しでメモを取る先輩たちの中で、私だけが授業についていけませんでした。
講義の内容はBGMのように右から左へとただ抜けていき、日に日に教室へ向かう足は重くなりました。
そして半年後、私は「自分には無理だ」と完全に自信を失い、静かにその講座からフェードアウトしていったのです。
「4年生になったら本気を出す」
それは、何もしない自分を正当化するための、都合のいい魔法の言葉でした。
周りの友人たちがインターンに行き、自己分析に悩み、次々と内定を決めていく。
その姿が眩しく見える一方で、私は「公務員になるから大丈夫」と平然を装い、内心ではとてつもない焦りと劣等感に苛まれていました。
その焦りから目を背けるように、私は意味もなくアルバイトのシフトを増やし、ただ時間を浪費していきました。
本気で勉強に向き合うことから、逃げ続けていたのです。
そして迎えた大学4年時の公務員試験。
もはや「記念受験」です。
ほとんど分からない問題で、鉛筆コロコロした答案用紙。
ただ試験時間が過ぎるのを待つだけでした。
試験会場からの帰り道、多くの受験生が手応えや反省を口にする中、私だけが何も語ることができず、晴れているはずの空が、なぜか灰色に見えたのを覚えています。
結果はもちろん、不合格。
気づけば私は、卒業証書だけを手に、社会という大海原に放り出された、進路未定の「既卒者」になっていたのです。
再起。退路を断った専門学校への道
そんな状況を見かねた両親と、卒業後、改めて将来について話し合いました。
「やはり、勉強して公務員になった方が良い。来年の試験に向けて、専門学校に通ってみてはどうか」
両親の言葉と、これ以上は逃げられないという自分の気持ち。
ここでようやく、就職や公務員に対して目を向け始めました。
「公務員になろう」
こうして私は、4月から公務員の専門学校に通い、ゼロから再スタートを切ることになったのです。
運命を変えた、叔父の一言
専門学校に通い始めたものの、正直なところ、まだ心のどこかに甘えがありました。
毎日、決まった時間に学校へ行き、人並みに勉強時間は確保する。
しかし、それは「やるべきこと」をこなしているだけ。
心の底から「絶対に合格するんだ」という熱意には、まだ火がついていませんでした。
そんな生ぬるい覚悟だった私に、本当のスイッチを入れたのは、ある日の親戚の集まりでの、叔父の一言でした。
私の進路について話が及んだ時、叔父は父に向かってこう言ったのです。
「(父)の子だから、こんなに出来が悪い。どんな教育をしていたんだ」
父は、その言葉を苦笑いで流していました。
しかし、その場にいた私の頭は、カッと熱くなりました。
「悔しさ」と「父を侮辱された怒り」です。
その瞬間、私の中で何かが完全に切り替わりました。
「絶対に、結果で見返してやる」
それまでの漠然とした目標が、初めて「公務員に絶対になる」という、燃えるような決意に変わったのです。
この日を境に、私の勉強への取り組み方は、全くの別物になりました。
勉強漬けの日々と、心の支え
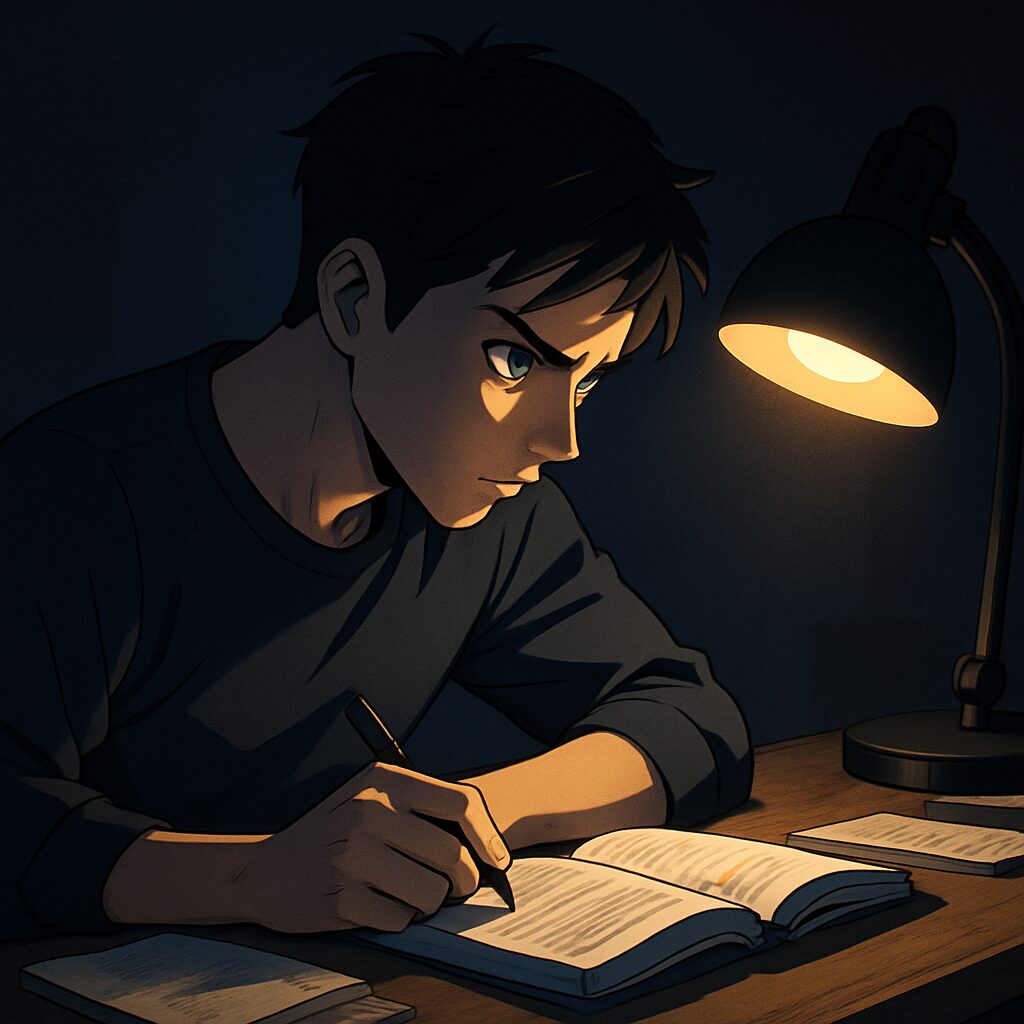
あの日を境に、私の生活は一変しました。
まず変えたのは、時間の使い方です。
「寝る時間以外、すべてを勉強に充てる」覚悟で、生活のすべてを再構築していきました。
- 朝5時起床
まずは頭をスッキリさせるために1時間のランニング。
思考がクリアになり、一日のスタートダッシュを切れました。 - 家での時間
ランニング後、家を出るまでの時間も、もちろん勉強。
特に頭を使う数的処理などの問題に取り組みました。 - 移動時間
往復の電車の中は、貴重な暗記時間に。
単語帳や、自分でまとめたノートの切れ端をポケットに忍ばせ、一つでも多く覚えることに徹しました。 - 日中の学習
私が通っていた専門学校は、収録された映像授業を各自で視聴するスタイルでした。
だからこそ、周りに流されず、以前とは比較にならない集中力で画面に向かいました。
他の人が談笑しているお昼休みも、私にとっては絶好の勉強時間でした。 - 帰宅後
食事中はもちろん、お風呂やトイレの中にまで参考書を持ち込む。
お風呂では、濡れてもいいようにクリアファイルに入れた暗記シートを壁に貼り付けていました。
まさに、生活のすべてを公務員試験に捧げたのです。
友達からの遊びの誘いも断りました。
正直、羨ましくて辛くなる日もありました。
でも、そんな時は決まって、あの日の叔父の言葉と、父の寂しそうな笑顔を思い出すのです。
「今やるべきことは一つしかない」と、自然と机に向かうことができました。
大胆な戦略。「専門科目、全部捨てました」
専門学校のコースは、1年後の試験に照準を合わせたものでしたが、私の心は「数ヶ月後に迫った、夏の試験での合格」に燃えていました。
学校側からは「サポート対象外」と言われましたが、もはや私の決意は揺らぎません。
では、残り数ヶ月という短期間で合格ラインに到達するには、どうすればいいか?
普通に全科目を勉強していては、絶対に間に合わない。まず、何から手をつけるべきか。いや、それ以上に「何を“やらない”べきか」を見極める必要がありました。
その戦略を立てるために、私はまず自分自身の残酷な現実と向き合いました。
よく「苦手科目はありましたか?」と聞かれますが、当時の私には、特定の苦手科目というものは存在しませんでした。
なぜなら、すべて科目が、できなかったからです。
ゼロからのスタートである以上、中途半端に全科目をかじるのは、合格から最も遠ざかる選択だと直感しました。
「周りのみんながやっているから」という理由で手を広げ、すべてが中途半端に終わることだけは避けたかったのです。
そこで私が下した決断は、「専門科目をすべて捨て、教養科目の一点突破で合格点を狙う」という、非常に大胆なものでした。
もちろん、「本当にこれでいいのか?」という不安がなかったわけではありません。
でも、限られた時間の中で結果を出すには、これしかないと信じて突き進むことにしました。
一冊を完璧に。私の反復勉強法
戦略は決まりました。
では、具体的にどう勉強したのか。
私が実践した方法は、とてもありきたりなものです。
それは同じ参考書(問題集)を、答えを覚えるまで何周も、何十周もすることでした。
- 1周目
まずは答えを見ながら解き進める。
解説を読んでも、正直チンプンカンプン。まるで宇宙語を読んでいるようでした。 - 2周目
ようやく、最初の方の簡単な問題が「見たことあるな」と感じるレベル。
手応えは全くなく、本当にこの方法で合っているのかと疑心暗鬼になりました。 - 4~5周目
このあたりから変化が訪れます。
不思議と「問題文をチラッと見ただけで、答えの選択肢が頭に浮かぶ」問題が出始めました。ここで初めて、微かな光が見えてきます。 - それ以降
さらに周回を重ね、最終的にはほとんどの問題で「答えを覚えてしまっている」状態に。
ここまでくると、問題を解くのが少し楽しくなってきました。
この「考えなくても体が反応する」レベルまで一冊をやり込むことで、知識は初めて自分の血肉になります。
新たな壁。過去問との戦い
参考書を完璧に仕上げた後、私は「過去問」の演習に入りました。
しかし、ここでも新たな壁にぶつかります。
参考書は完璧なはずなのに、過去問になると、点が取れない…
問題の問われ方や角度が少し違うだけで、途端に解けなくなるのです。
ここで一度、自信を失いかけましたが、やることは同じでした。
解けなかった問題を完璧に理解し、最終的には問題文を見ただけで、瞬時に解法が浮かぶレベルまで、過去問もまた、何周も何周もやり込みました。
【第2章】本当の勝負。独学で挑んだ面接と論文
孤独な挑戦。二次試験、始まる
夏の試験で見事、筆記試験を突破。
しかし、喜んだのも束の間、すぐに次の壁が立ちはだかります。
そう、面接と論文です。
学校のサポートは、もちろん受けられません。
ここからは、完全に自分一人で道を切り拓くしかありませんでした。
両親と、二人三脚の面接練習

まず、面接対策。
私が頼ったのは、一番身近な存在である両親でした。
毎晩2時間、父と母を試験官に見立てた、実践形式の模擬面接。
これを、一日も欠かさず続けました。
- 実践
両親から、「志望動機」「自己PR」といった基本的な質問から、「最近気になるニュースは?」「あなたの短所と、それをどう克服しようとしていますか?」といった少し意地悪な質問まで、様々な角度から問いを投げかけてもらう。 - 反省会
模擬面接が終わるたびに、3人で反省会。
「今の答えは分かりにくかった」「もっとハキハキ話した方が良い」といった見た目の指摘から、「そのエピソードではあなたの強みが伝わらない」「もっと具体的に話すべき」といった内容面の指摘まで、出てきた課題をすべてメモする。 - 修正
次の日の模擬面接で、指摘された点を修正していく。
この泥臭い繰り返しが、私の自信と実力を着実に引き上げてくれました。
論文の鍵は「自治体への愛」でした
論文対策の基本も「過去問の繰り返し」でした。
しかし、それだけでは足りないと感じた私が、特に意識したことがあります。
それは、受験する自治体のことを、誰よりも詳しくなるということです。
私が徹底的に調べたのは、その自治体が何を目指しているのかということでした。
- 総合計画を読み込む
- 首長のメッセージを分析する
- 最近の広報誌やニュースをチェックする
これらの情報から「自治体が求めている人物像」を自分なりに描き出し、論文のテーマと結びつけていきました。
この「相手を知る」という視点は、試験が終わった後、「自分の選択は間違っていなかった」と確信に変わりました。
【最後に】私が合格して、本当に大切だと感じたこと
大学時代に一度は挫折し、進路が決まらないまま卒業した私が、こうして合格体験記を書いている。
人生、本当に何が起こるか分かりません。
特別な才能も、強い意志もなかった私が、合格を掴み取るために必要だったもの。
それは、たった一つの、シンプルなことだったように思います。
「絶対に合格する」という、腹の底からの決意。
私の場合は、叔父の一言という「怒り」が原動力でしたが、きっかけは何でもいいのだと思います。
- 誰かを見返したい
- 安定した生活が欲しい
- この街が好きだから貢献したい
その気持ちが本物で、自分のすべてを懸けられるほど強いのなら、それは合格に向けた最強のエンジンになります。今、先の見えないトンネルの中で、不安と戦っているあなたへ。
大丈夫!その苦しい経験は、決して無駄にはなりません。
この記事が、あなたの「本気のスイッチ」を入れる、小さなきっかけになることを心から願っています。
以上、ごんでした。



