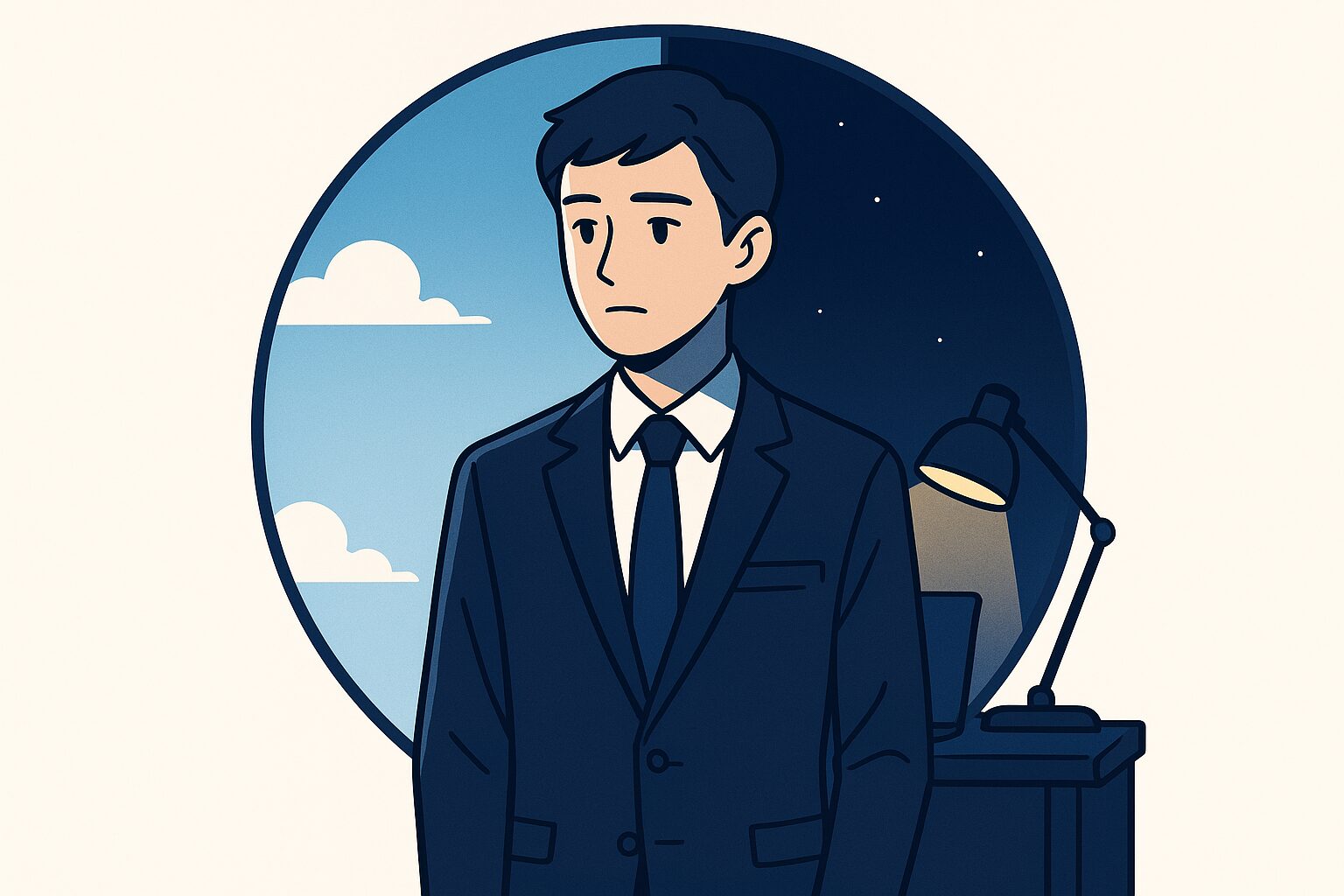現役公務員の、とある一日。
あなたは、どんな姿を想像しますか?
きっかり8時30分に出勤し、お昼は食堂で同僚と談笑。夕方5時過ぎには「お疲れ様でした!」と、颯爽と庁舎を後にする、平和な毎日…?
それとも、鳴り止まない電話と大量の書類に追われ、気づけば窓の外は真っ暗。深夜までデスクにかじりつく、過酷な毎日…?
実は、そのどちらもが、公務員にとっての「リアルな一日」なんです。
この記事では、私が実際に経験した、天国と地獄のように全く異なる2つの「とある一日」を、タイムライン形式で赤裸々にレポートします。
配属される部署や時期によって、これほどまでに違う公務員の日常。 『暮らし整える課』の、リアルな業務日誌を覗いてみませんか?
【定時退庁】公務員の平和な1日タイムスケジュール
まずは、「終電コース」に比べれば天国のように感じられた「定時で帰れた日」の一日から見ていきましょう。 世間でイメージされるほど穏やかではありませんが、私にとってはこれが「平和な一日」でした。
8:30 始業
出勤後、自分のデスクで準備をする間もなく、すぐに課の「朝礼」が始まります。
これが毎日の恒例でした。
司会は日替わりの当番制。
まず係ごとに、その日の職員の外出予定や会議の有無などを全員で共有します。その後、課長から一言があり、最後に司会が今日の話題を一分程度話して(これが意外とプレッシャーでした…笑)、業務がスタートします。
もちろん、朝にゆっくりコーヒーを淹れたり、同僚と雑談したりする時間はありません。それどころか、朝礼の最中から窓口のチャイムが鳴ったり、問い合わせの電話が鳴り響いたりすることも日常茶飯事でした。
10:00 午前業務
朝礼が終わると、一気にエンジンがかかります。 「自分のペースで計画通りに」なんて優雅な時間はほとんどありません。
午前中は、市民の方からの問い合わせ電話に対応しつつ、急ぎの会議資料を作成したり、他部署から依頼された調査物をまとめたりと、複数のタスクに常に追われている状態です。 窓口に直接来られる方もいるので、その対応も入ってきます。
ただ、この日はそれぞれのタスクが順調に進み、大きなトラブルもなく、一つ一つ着実に終わらせていける。
そんな「普通」が、とてもありがたい時間です。
12:00 昼休み
12時になり、庁内にチャイムが鳴り響きますが、心から休まる時間ではありません。
先輩や上司たちは外へランチに出かけたり、自分の机で仮眠をとったりしていますが、新人である私は自分のデスクでお弁当を広げます。 なぜなら、お昼休み中でも、窓口に住民の方が来られたり、問い合わせの電話が鳴ったりすることは日常茶飯事だからです。
いつ呼ばれても対応できるように、席を外すことはほとんどありませんでした。
お弁当を食べながら、午後の業務の段取りを頭の中で整理する。
これが、私の「平和な日」の昼休みのリアルです。
13:00 午後業務
午後は、市民の方からの問い合わせ対応や、関係機関との電話調整がメイン。 たまに少し複雑な案件もありますが、一つ一つ丁寧に対応していきます。夕方には、課内の小さな打ち合わせで、明日の業務の段取りを確認。スムーズに情報共有ができました。
18:30 退勤
17時15分、定時のチャイムが鳴りますが、すぐに「さようなら!」とはなりません。 そこから、やりかけの業務をキリの良いところまで進めたり、明日の準備をしたり、デスク周りを片付けたり。なんだかんだで、庁舎を出るのはいつも18時半頃になっていました。
それでも、世間がまだ活動している時間に帰れるというのは、精神的に大きな違いです。 空がまだ完全に真っ暗になる前に帰路につける。
私にとって、これが「早く帰れた日」の基準でした。
20:00 帰宅後の時間
18時半に庁舎を出て、寄り道などをしていると、帰宅するのは20時前くらいになります。 そこから夕食をとり、少し休憩する。
正直に言うと、私は仕事のことをずっと考えてしまうタイプなので、この時間も頭のどこかで明日の業務の段取りを考えていたりします。 「よし、また明日も頑張ろう!」と前向きに切り替えられることは、あまりありませんでした。
それでも、物理的に職場から離れ、強制的にでも自分の時間を作ることに、大きな意味がありました。 読書をしたり、好きなドラマを少し見たり。その時間は、常に仕事のプレッシャーに晒されている心にとって、唯一の避難所のようなもの。
この時間があったからこそ、なんとか翌日も出勤できていたのだと思います。
【深夜残業】公務員の過酷な1日タイムスケジュール

さて、ここからはもう一つの現実、「過酷な一日」のタイムラインです。 18記事目でお話しした、私が心身のバランスを崩すきっかけとなった部署での、典型的な一日です。
始業前
この日の戦いは、多くの人がまだ夢の中にいる時間から始まります。 時には朝5時や6時に出勤することもありました。定時出勤では到底間に合わない、絶望的な量の仕事がデスクで待っているからです。
まだ誰もいない、静まり返ったオフィスで一人、PCの電源を入れる。 コーヒーを飲む余裕などもちろんなく、今日一日をどう乗り切るか、必死に頭の中で戦術を組み立てます。
8:30 午前業務
始業のチャイムは、開戦のゴングです。
鳴り止まない内線と外線、上司からの「これ、急ぎでお願い」という無茶振り、他部署からの問い合わせ…。それに加え、毎日必ず締め切りがやってくる調査物が、常に複数抱えている状態でした。
一つの作業に集中しようとすると、必ず何かに横槍を入れられる。マルチタスクという聞こえの良い言葉では表せない、ただのカオスです。
12:00 昼休み(という名の戦闘配給)
昼休みは、実質5分。
栄養補給という名の戦闘配給の時間です。
運が良ければ、売店で買ったおにぎりをデスクで頬張りながら、PCの画面とにらめっこできます。 もちろん、同期と食堂に行くなんて、夢のまた夢。 それどころか、電話対応や急な業務に追われ、その5分すら確保できずに、昼食を抜いてしまう日も、珍しくありませんでした。
空腹を紛らわすために、ただお茶を飲む。
この時間も、少しでも業務を進めなければ、午後がさらなる地獄になることが分かっているからです。
13:00 午後業務
午後は、さらにプレッシャーのかかる仕事が続きます。 偉い人が出席する会議の資料の最終チェックや、絶対にミスが許されないデータの入力作業。一つ一つのクリックに、神経がすり減っていくのを感じます。 疲労で低下した集中力を、気力だけでなんとか繋ぎ止めている状態です。
17:15 「定時」という名の、第二ラウンド開始
定時のチャイムが、虚しく響きます。フロアを見渡しても、帰る準備をしている人など一人もいません。 むしろ、「ここからが本番だ」という、静かで重い空気が漂い始めます。 日中の緊急対応で後回しにしていた、本来やるべきだった自分の仕事に、ようやく取り掛かる時間です。
22:00 深夜残業
時計の針はとっくに22時を回り、思考力は限界に。栄養ドリンクの缶だけが、デスクの上に増えていきます。
私は車通勤だったので、終電というタイムリミットはありませんでした。 しかし、それは「終わりがない」ということでもありました。
「どこまでやれば、帰れるんだろう…」。
頭の中で繰り返されるのは、そんなゴールが見えない問いだけ。 仕事のクオリティなど、もはや考える余裕はありません。ただ、この終わらない作業に少しでも区切りをつけるためだけに、指を動かし続けます。
26:00(深夜2:00) 退勤
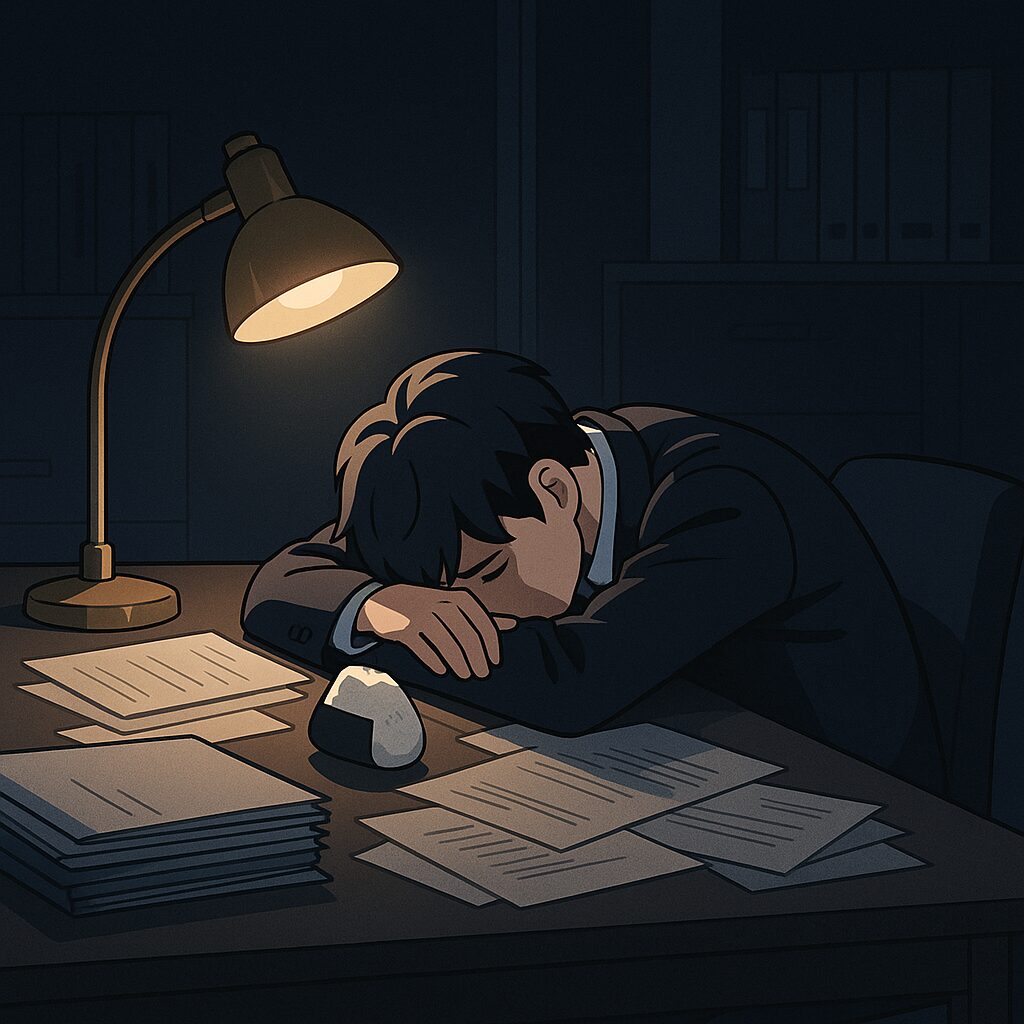
気づけば、窓の外は完全な闇に包まれ、日付もとっくに変わっていました。 ようやくキリをつけてPCをシャットダウンしたのが、深夜2時。
疲労困憊の体を引きずり、誰もいない庁舎の廊下を歩く。自分の足音だけが、やけに大きく響きました。 家に帰っても、食事もそこそこにベッドに倒れ込むだけ。そして、数時間後にはまた、同じ戦いが始まるのです。
ひどい時には、この家に帰るという選択肢すらなく、仮眠のために数時間だけ机に突っ伏して、そのまま朝を迎えることもありました。
なぜ、ここまで違うのか?
定時より少し遅い18時半には帰れた日と、深夜2時を過ぎ、時には庁舎で朝を迎えた日。
同じ「公務員」という仕事なのに、なぜ、ここまで極端な違いが生まれるのでしょうか。 私の経験上、その理由は主に3つの要因に分けられると思います。
要因①:所属する「部署」の特性
公務員の仕事は、驚くほど多岐にわたります。 市民の方と直接やり取りする「窓口系の部署」もあれば、街の将来計画を練る「企画系の部署」、そしてお金を管理する「財政系の部署」など、その役割は様々です。
一般的に、突発的な業務が少なく、ルーティンワークが中心の部署は残業が少なくなる傾向にあります。一方で、議会対応や予算編成などを担当する部署は、どうしても業務が集中し、激務になりがちです。
要因②:構造的な「人手不足」
「繁忙期を乗り越えれば楽になる」——
そう思えれば、まだ救いがあったかもしれません。 しかし、私が配属された部署には特定の繁忙期というものはなく、一年間を通して、常に業務に追われ、休まる日はありませんでした。
その最大の理由は、構造的な人手不足です。 もともと職員が少ない部署だったことに加え、前年度まで2人がかりで担当していた業務を、人員削減によって、私一人で引き継ぐことになったのです。
つまり、単純計算で、常に2人分の仕事量を一人でこなさなければならない状況でした。 ポジティブに考えれば、「私にならできる」と期待してもらえたのかもしれません。
しかし、いくら業務に慣れてきたとはいえ、それはあまりにも重すぎる荷物でした。
要因③:良くも悪くも「上司」次第
そして、最も大きいのが、この「上司」の存在かもしれません。 効率的に仕事をこなし、部下を早く帰らせようと考えてくれる上司もいれば、残念ながら、そうではない上司もいます。
例えば、業務の優先順位を明確にし、部下を守ってくれる上司の下では心穏やかに働けますが、指示が曖昧で、精神論を振りかざす上司の下では、疲弊してしまいます。 上司の仕事の進め方や、残業に対する考え方一つで、課全体の雰囲気や働き方は、驚くほど変わってしまうのです。
こればかりは、配属されてみないと分からない「運」の要素も大きいのが実情です。
【まとめ】どんな一日も、自分らしく乗りこなすために
定時より少し遅い18時半には帰れた「平和な日」と、深夜2時を過ぎ、時には職場で朝を迎えた「過酷な日」。 今回は、私が経験した2つのリアルな一日をご紹介しました。
公務員と一言で言っても、その働き方は配属先や時期によって、天国と地獄ほども違う。これが、私が身をもって知った現実です。
そして、この経験から学んだことがあります。 それは、どんなに職場環境が変わろうとも、その中で心と体のバランスを保ち、自分自身の暮らしを「整える」ことの重要性です。
平和な日には、その余裕を自分の心の栄養にする。 過酷な日には、どうやって自分の心身を守り、乗り切るかの術を持つ。
このブログ『暮らし整える課』は、そんな激しい環境の波を、自分らしく乗りこなすためのヒントを、私の経験を通して発信していきたいと思っています。
この記事が、これから公務員を目指す方にとっては、仕事の多面性を知るきっかけに。 そして、今まさに現場で奮闘している方にとっては、「自分だけじゃないんだ」という、少しの安らぎになれば、これほど嬉しいことはありません。
もし、あなたが同じような状況に置かれたなら、この「平和な一日」と「過酷な一日」を、どう乗りこなしますか?
ぜひ、あなたの考えも聞かせてください。