こんにちは、ごんです。
突然ですが、皆さんは、将来のために「漠然としたお金の不安」を抱えていませんか?
- このままで、老後の生活は大丈夫だろうか…
- 子どもの教育費って、一体いくらかかるんだろう…
- 親の介護が必要になったら、どうしよう…
考えればキリがない、お金の悩み。
私自身、もともとお金について考えるのは好きな方でした。今の妻と交際を決めた30分後には、カフェで将来のお金の話を切り出したくらいです(普通なら、ドン引きですよね(笑))。
でも、そんな私でさえ、数年前の大きな失敗(投資詐欺)をきっかけに、一度ゼロから、いや、マイナスからのスタートで、本気で「家計管理」と向き合うことになりました。
そこで今回は、そんな私が実践している、誰でも今日から始められる、ゆるくて効果的な家計管理術についてお話しします。
この記事で紹介するのは、難しい専門知識や、根性で乗り切るような節約術ではありません。
「ズボラな私でも続けられている」、そんな具体的で簡単な3つのヒントです。
この記事を読み終えて実際に行動すれば、お金への不安が、少しだけ「未来への安心」に変わっているかもしれません。
まずは現状把握から
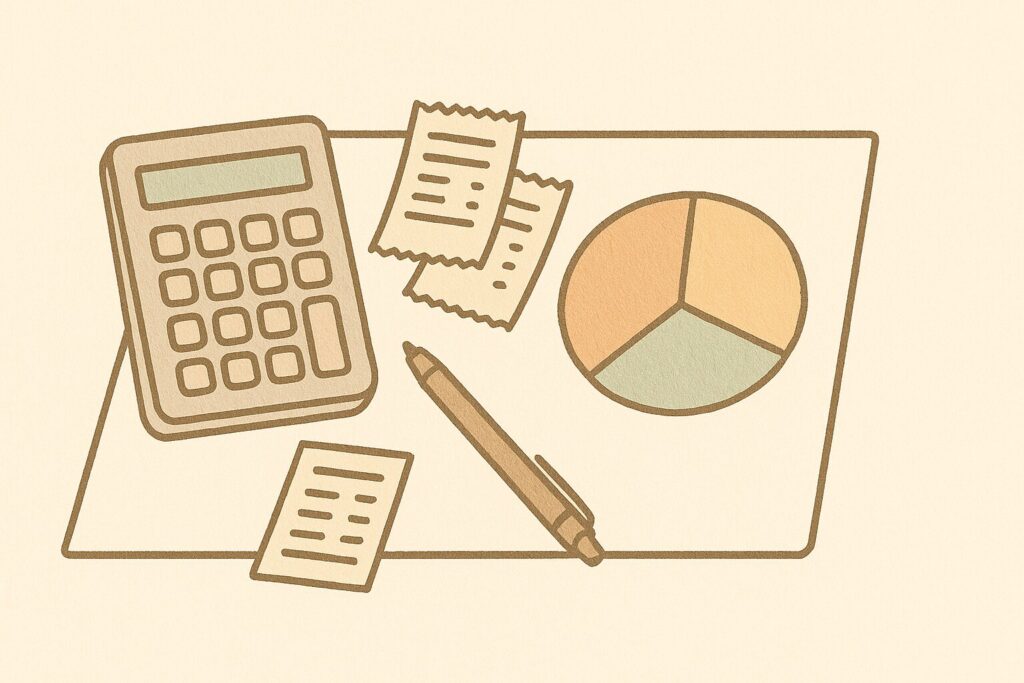
最初のステップ「家計簿アプリの導入」
何から手をつければいいか分からなかった私が、まず最初に行ったのは、家計簿アプリ「マネーフォワード ME」を導入することでした。有料プランに課金し、「これで家計を自動で見える化できるぞ!」と意気込んでいました。
しかし、そこで早速、最初の壁にぶつかります。 それは、「銀行口座とクレジットカードが、多すぎる…!」という問題でした。
私自身はそんなに多くないと思っていたのですが、改めて整理しようとすると、すっかり忘れていた銀行口座なども見つかりました。妻も、学生時代に作ったまま使っていない口座やクレジットカードが、思った以上にたくさんあったのです。
お恥ずかしながら、私自身も全く使っていない口座に数千円が残っているのを発見し、「このお金のこと、忘れてたなんて…」と愕然としました。
「これは、家計簿をつける前に、まず断捨離が必要だ!」 そう思い、私たちは重い腰を上げて、銀行口座とクレジットカードの整理から始めることにしました。
口座とカードの断捨離。現金派からの卒業
具体的な我が家の断捨離は、以下の通りです。
- 私
銀行口座6つ→2つ
クレジットカード3枚→1枚に - 妻
銀行口座4つ→2つ
クレジットカード4枚→2枚に
しかし、この口座とカードの整理、実は思った以上に時間がかかりました。 なにせ、銀行の窓口は平日の日中しか開いていません。
そのため、わざわざ年次有給休暇を取得して、解約手続きのために銀行をハシゴすることも…。結局、夫婦二人分の使っていない口座やカードを全て整理し終えるまでに、数ヶ月もかかってしまいました。
でも、この手間をかけてでも断捨離したことで、その後の家計管理が驚くほど楽になったんです。
そして、もう一つ大きな変化がありました。
それは、私が「現金派」から「キャッシュレス派」に完全に移行したことです。 もともと現金での支払いが好きだったのですが、現金だとマネーフォワード MEへの入力が手間で、どうしても記録漏れが出てしまいます。慣れないカードでの支払いは最初は少し不安でしたが、一度慣れてしまうと、もう現金派には戻れなくなりました。
家計簿アプリで「支出の見える化」をしてみたら…
口座やカードの整理を終え、本格的にマネーフォワード MEでの家計管理がスタートしました。 クレジットカードや銀行口座を連携させるだけで、ほとんど自動で家計簿を作成してくれるので、これはもう、今の我が家にはなくてはならない存在です。月額料金はかかりますが、その効果を考えれば安いものだと感じています。
もちろん、最初は操作に慣れなかったり、費目の分類に悩んだりもしました。(今でも、「この支払いはどの分類だっけ?」と妻と話し合いながら、我が家なりのルールを決めて振り分けています。)
そして、支出を「固定費」と「変動費」に分けて見える化してみて、いくつかの衝撃的な事実に気づきました。
- 「外食費」が、思ったより高かった!
自分たちではそこまで外食しているつもりはなかったのですが、数字で見ると、食費の中でかなりの割合を占めていて驚きました。 - 「固定費」は、やっぱり侮れない!
保険料や通信費など、毎月「こんなものかな」と思っていた固定費も、塵も積もれば山となるものです。月々500円でも、見直せるものは見直すべきだと痛感しました。一度見直せば、その効果がずっと続くのが固定費のすごいところです。
家計管理というと、つい日々の食費などの「変動費」に目が行きがちですが、まずは一度見直せば効果が続く「固定費」から手をつけるのが、一番おすすめです。そこが安定すれば、あとは毎月の変動費だけを意識すれば良くなるので、気持ち的にもぐっと楽になりますよ。
見直しで効果絶大だった!3つのポイント
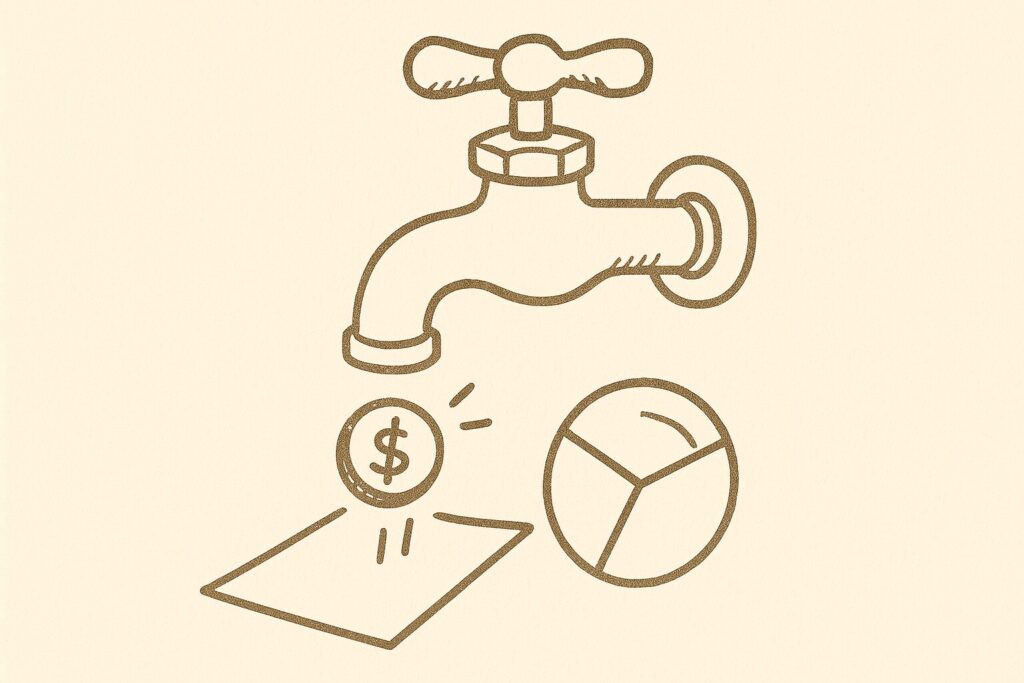
ポイント①:固定費の削減
家計管理と聞くと、日々の食費や雑費を切り詰める「節約」をイメージする方が多いかもしれません。でも、私が一番最初におすすめしたいのは、一度見直せばその効果がずっと続く「固定費」の削減です。先ほども少し触れましたが、我が家が実際に見直して、特に効果が絶大だった2つの固定費についてお話しします。
① 通信費:スマホを格安SIMに変えるだけで、年間20万円以上の衝撃
まず、最も劇的な効果があったのが、夫婦2人分のスマートフォンなどの通信費です。
- 私
au(月9,000円程度)
→ UQモバイル(月4,000円程度)
→ 日本通信SIM(現在月1,300円程度) - 妻
SoftBank(本体分割払い込みで月12,000円程度)
→ UQモバイル(月4,000円程度)
→ 日本通信SIM(現在月1,300円程度)
夫婦二人で、かつては合計で月に21,000円ほど支払っていた通信費が、今では月に2,600円ほどになりました。 その差はなんと、月々約18,400円、年間で計算すると約22万円にもなります。
正直、格安SIMに変えるのは少し手間がかかるイメージがありましたが、実際にやってみると、その手間を補って余りあるほどの大きなインパクトがありました。 また、この見直しをきっかけに、「分割払いでないと買えないものは、今の自分には分不相応だ」と考えるようになり、スマホ本体の分割払いもやめました。この心の変化も、大きな収穫の一つです。
② サブスク:本当に必要?「思考停止で継続」をやめる
次に手を入れたのが、毎月なんとなく支払っていたサブスクリプションサービスです。
我が家では、Netflix(月額1,590円)とLINE MUSIC(月額980円)を解約しました。
私個人としてはNetflixをよく利用していたのですが、よくよく考えると、Amazonプライムにも加入しており、プライムビデオで十分代替できることに気づきました。Amazonプライムは普段の買い物にも使うので、解約という選択肢はありません。そこで、同じ動画配信サービスであるNetflixを手放すことにしました。LINE MUSICも同様の理由です。
これで、月々約2,570円、年間で計算すると約3万円の固定費を削減できました。
固定費の見直しは「思考の断捨離」
私が固定費の見直しで感じたのは、物の断捨離と同じように、頭の中がクリアになる感覚でした。 スマホやサブスクは、部屋のスペースを取るわけではありません。でも、「今月もあの支払いがあるな」と無意識に考え続けている状態は、確実に「思考のスペース」を奪っています。 それらを手放すことで、お金が貯まるだけでなく、心が軽くなり、もっと大切なことについて考えるための余白が生まれる。これが、固定費の見直しがもたらしてくれた、お金以外のメリットかもしれません。
ポイント②:支出のルール作り
家計の現状が見えてきたら、次に取り組みたいのが、夫婦で協力してお金を管理していくための「ルール作り」です。
このルール作り、最初から完璧を目指す必要はありません。我が家も、実際に家計簿をつけながら、二人で話し合って、1年くらいかけて少しずつ今の形になってきました。これは「終わり」があるものではなく、今も夫婦で協力しながら、より良い形を模索している最中です。
でも、このプロセスを通して、自然と将来の話をする機会が増えたり、家計が目に見えて改善していくのは、とても楽しくて嬉しいですよ。
今回は、そんな我が家で実践している2つのルールをご紹介します。
ルール①:月に一度の「カフェ家計会議」
我が家では、月に一度、必ず「家計会議」を開いています。
「休日にわざわざ家計簿と向き合うのは、気が重いな…」と感じる方もいるかもしれません。だからこそ、我が家ではこの会議を「カフェで行う」と決めているんです。
家でやると、リラックスしすぎてついダラダラしてしまったり、時には少し気まずい雰囲気になったりすることもありました。でも、カフェという「外の空間」なら、良い意味で周りの目があるので、私たちも少し客観的に、そしてテキパキと話を進めることができます。
「家計管理のためにカフェに行く」というよりは、「カフェに行くついでに、ちょっと家計の話をする」くらいの感覚ですね。新しいカフェを開拓する楽しみもありますし、これなら無理なく続けられます。(いつもはスターバックスのテラス席や、サイゼリヤ、ガストのようなファミレスを利用することが多いです。)
ルール②:ボーナス支給の「お小遣い制」
もう一つのルールが、「お小遣い制」です。
これは、無駄遣いを防ぎ、貯蓄や投資に回すお金をしっかり確保するために始めました。我が家では仕事のように毎月の「予算」を決めているので、お互いが欲しい金額を無制限に計上すると、どうしても予算オーバーになってしまうのです。
ちなみに、我が家のお小遣いは、私が月1万円、妻が月1.5万円で、それを年2回のボーナス月にまとめて受け取る、という少し変わった方式をとっています。
これは私たち夫婦が、現在の収入や、将来のための貯蓄・投資計画を何度も話し合った上で決めた、今の私たちにとって最適な金額なんです。もちろん、我慢する部分もありますが、二人で納得したルールなので、全く問題ありません。
ここで一番大切なのは、金額そのものではなく、「夫婦で話し合い、お互いが納得できるルールを見つけること」だと思います。
ご家庭の収入やライフスタイルによって、最適な形はそれぞれ違うはずです。ぜひ、他の誰かと比べるのではなく、ご自身の家庭に合った、無理なく続けられるルールを見つけてみてください。
ポイント③:未来の安心を作る「お金の仕分け」と「先取り貯蓄」
固定費を見直し、夫婦でお金のルールを決めたら、いよいよ最後のステップです。 それは、「未来の安心」を作るためのお金の置き場所を先に決めてしまうことです。
貯める前に、まず「仕分け」する
家計管理を始めたばかりの頃は、「余ったお金を貯蓄に回そう」と考えていました。でも、この方法だとなかなかお金は貯まりません。 そこで我が家では、まず「お金の仕分け」から始めることにしました。
- 今年中に必要なお金
冠婚葬祭や年払いの費用などを、まず確保する。 - 数年以内に必要なお金
例えば、5年後に100万円必要なら、年間20万円、月々約1.5万円、といった形で、次に確保する。 - そして、残った本当の「余剰資金」
余剰資金の中から、無理のない範囲で少しだけ投資に回す。
このように、目的別に先にお金を仕分けておくことで、「これは使ってはいけないお金」と「これは自由に使えるお金」が明確になり、計画的に未来への備えができるようになりました。
「貯めすぎ」にも注意?我が家の夫婦会議
ただ、この「貯蓄」や「投資」のバランスは非常に難しく、私たち夫婦も、今も話し合いながら模索している最中です。
心配性な私は、つい貯蓄の割合を増やしすぎて、今の生活を切り詰めてしまうような予算を立ててしまうことがあります。でも、妻から「明日、何があるか分からないんだよ?」と言われて、ハッとさせられる。 未来への備えはもちろん大切ですが、それによって「今」の生活や楽しみを犠牲にしすぎるのも、違うのかもしれません。
我が家では、「満足度が下がらない支出」は見直しつつ、「満足度が上がる支出(例えば、たまの外食や趣味など)」は大切にする、というバランスを、夫婦で話し合いながら探しています。
家計管理がくれた、本当の「安心感」
家計管理を始め、こうして「未来のための備え」を仕組み化できたことで、私の心には大きな変化がありました。 もちろん、将来への不安がゼロになったわけではありません。
でも、漠然としていた不安が、「これだけ備えているから大丈夫」という、具体的な安心感に変わってきたのです。
そして意外なことに、毎月の予算を決めたことで、以前よりも少しだけ、お金を使うことへの罪悪感が減りました。「この範囲の中なら、自分の好きなことに使って良いんだ」と思えるようになったからです。(それでもまだ、なかなか大胆には使えませんが(笑))
家計管理は、ただ支出を減らすだけの作業ではありません。未来への安心感を育て、そして「今」を心地よく生きるための、道しるべなのだと、私は思っています。
まとめ:家計管理は「未来の安心」を手に入れるための、最高のよりみち

今回は、我が家が実践している、共働き公務員夫婦のリアルな家計管理術についてお話ししてきました。
私が家計管理を始めて一番良かったと感じているのは、漠然としていた将来への不安が、「これだけ備えているから大丈夫」という、具体的な安心感に変わったことです。 そして、「お金のことで悩む時間」が減ったことで生まれた「心の余裕」は、日々の暮らしをより豊かなものにしてくれました。
もし、あなたが今、お金のことで漠然とした不安を抱えているなら、まずは完璧を目指さなくて大丈夫です。
「節約しなきゃ」「投資しなきゃ」と焦る前に、まずは「自分の家の現状を知る」という、小さな一歩からで全く問題ありません。
家計管理は、未来の自分と家族の暮らしを楽にしてあげるための、最高の自己投資だと私は思います。 この記事が、あなたがその一歩を踏み出す、小さなきっかけになれたなら、とても嬉しいです。
以上、ごんでした。



