こんにちは、ごんです。
突然ですが、皆さんは「ふるさと納税」、やっていますか?
「お得な制度らしい」と頭では分かっていても、
- 「なんだか手続きが複雑で、つい後回しにしてしまう…」
- 「返礼品の種類が多すぎて、結局どれがお得なのか選べない…」
- 「そもそも仕組みがよく分からない…」
といった理由で、まだ手を出せていない、という方も多いのではないでしょうか。 実際に、私の親族も「よくわからないし、めんどくさそうだからやらない」「スマホやPCの操作が苦手で…」と話していました。
豪華なグルメ品やお肉が注目されがちですが、実はもっと地味で、でももっと生活に密着した、驚くほど合理的な活用法があるんです。
そこで今回は、そんな私がたどり着いた、『グルメ品』ではなく『日用品』を選ぶという、超合理的で生活が劇的に楽になるふるさと納税活用術をご紹介します。
この記事を読めば、ふるさと納税に対するハードルがぐっと下がり、「これなら私にもできるかも!」と思っていただけるはずです。
なぜ、我が家は「日用品」を選ぶのか

きっかけは「パンパンの冷凍庫」と「筋トレ」
ふるさと納税といえば、やはり豪華なお肉や旬のフルーツといった「グルメ品」が魅力的ですよね。 もちろん私も、2020年にふるさと納税を始めてからしばらくは、ランキング上位のグルメ品を選んでいました。筋トレに励んでいた時期には、冷凍の鶏むね肉やもも肉を大量に注文したこともあります。
でも、そこで一つの問題に直面しました。「冷凍庫が、パンパンで何も入らない…!」 嬉しい悲鳴ではあるのですが、届くタイミングを調整するのも難しく、他の冷凍食品が買えなくなってしまうことも。
また、日々の暮らしの中で「ティッシュやトイレットペーパーの買い物って、地味にかさばって大変だな」「この買い物の手間を減らせたら、もっと楽になるのに」と常々感じていました。 ちょうど筋トレ中で食事内容に気を使っていたこともあり、「食べ物以外の日用品にしてみたらどうだろう?」と考え始めたのが、我が家が「日用品特化」のふるさと納税に切り替えたきっかけです。
買い物の手間と「考えるコスト」から解放される、3つのメリット
実際に日用品に切り替えてみて、私が感じたメリットは大きく3つあります。
- 「切らしてしまう」心配からの解放
ティッシュ、トイレットペーパー、キッチンペーパー。これらは生活必需品ですが、うっかり切らしてしまうと地味に困りますよね。ふるさと納税で大容量のものが年に一度届くようになってから、「あ、ティッシュのストックがない!」といった心配や焦りがなくなりました。これは精神的に非常に大きいです。 - 「買い物リスト」からの解放
常に頭の片隅にあった「そろそろトイレットペーパーを買わなきゃ」といった思考。
この「考えるコスト」がなくなったことで、頭の中がスッキリしました。買い物リストからこれらの項目が消えるだけで、日々の負担がぐっと軽くなります。 - 「かさばる物を運ぶ」肉体労働からの解放
ティッシュやキッチンペーパーは、軽いけれどかさばる物の代表格。買い物に行くと、それだけで片手がふさがってしまうのが、ずっと嫌でした。ふるさと納税なら、それらを玄関先まで届けてくれる。この快適さは、一度味わうとやめられません。
夫婦での自然な役割分担
ちなみに、我が家では「私が日用品担当、妻がグルメ品担当」という、大まかな役割分担が自然とできています。 特に厳密に話し合って決めたわけではなく、私が毎年同じ日用品を頼み、妻はその年の気分で楽しみたいグルメ品や贅沢品を選ぶ、というのが基本スタイル。
もちろん、寄付金の上限額を調整するために、お互いの担当を交換して、妻が日用品を選んだり、私がグルメ品を選んだりすることもあります。
このように、夫婦で柔軟に楽しみながら、協力して制度を活用できるのも、ふるさと納税の魅力の一つかもしれません。
私が実際にリピートしている!おすすめ日用品返礼品
私が毎年「これ!」と決めてリピートしている、おすすめの日用品返礼品を、実際の寄付履歴を元にご紹介します。
ポイントは、普段から使い慣れている、安心できる大手メーカーの製品を選ぶことです。品質が安定していますし、「思っていたのと違った…」という失敗がありません。
おすすめ①:トイレットペーパー
まず1つ目は、毎日使うトイレットペーパーです。
昨年は、静岡県富士宮市の「エリエール トイレットティシュー(コンパクトダブル)64ロール」を選びました。寄付金額は16,000円でした。
私がこれだけは譲れないこだわりは、トイレットペーパーは絶対に「ダブル」を選ぶということです!シングルではどうもお尻が許してくれない、と言いますか…(笑)。
ここは好みが分かれる部分かもしれませんが、返礼品を選ぶ際には、ぜひ皆さんもご自身の「小さなこだわり」を大切にしてみてください。 普段から使っているブランドなので、使い心地も分かっていて安心です。64ロールという大容量が一度に届くので、一年近くトイレットペーパーの残りを心配したり、買いに走ったりすることがなくなり、本当に快適です。
おすすめ②:ティッシュペーパー
2つ目は、何かと消費が激しいティッシュペーパー。
こちらは、栃木県佐野市の「エルモアティシュー 200組5箱×12パック(合計60箱)」を選びました。寄付金額は12,000円でした。
60箱もあれば、各部屋に置いても、しばらく買い足す必要がありません。これも、日々の「考えるコスト」を減らしてくれる、お気に入りの返礼品です。
おすすめ③:キッチンペーパー
3つ目は、料理や掃除に欠かせないキッチンペーパー(キッチンタオル)です。
こちらは、徳島県阿南市の「ネピア 激吸収キッチンタオル 12パック(100カット×4ロール×12パック)」を選びました。寄付金額は16,000円でした。
吸水性が高く、丈夫なので、気兼ねなく使えるのが良いですね。これも大容量なので、一度届くと長持ちし、非常に助かっています。
初心者でも簡単!ふるさと納税の始め方3ステップ
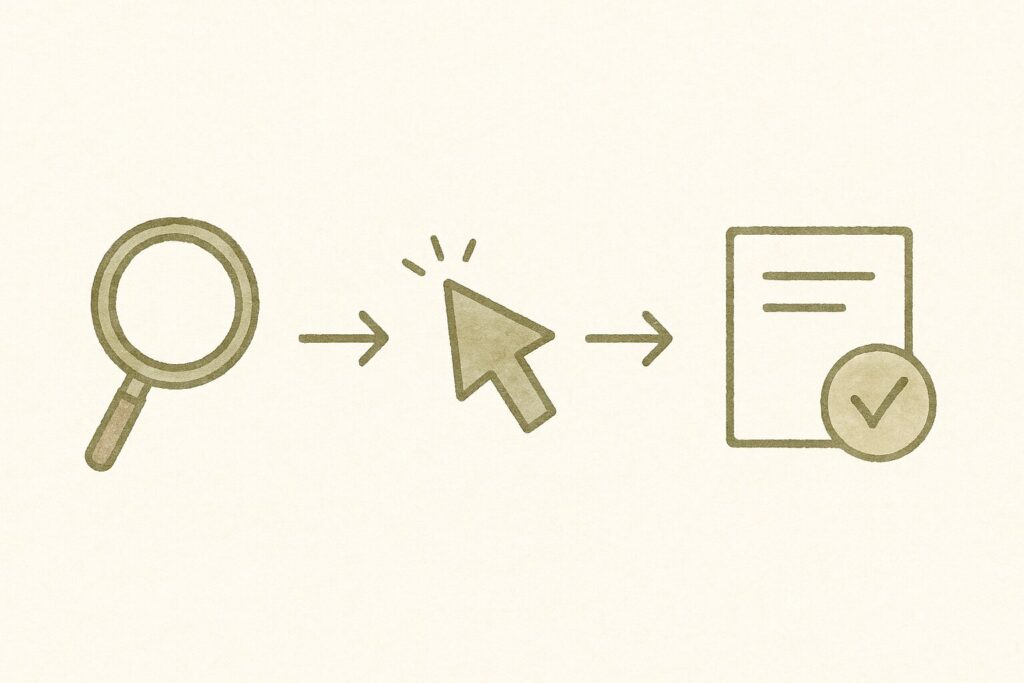
「でも、やっぱり手続きが難しそう…」と感じる方のために、私が実践している、驚くほど簡単なふるさと納税の始め方を3つのステップでご紹介します。
私はいつも「さとふる」というサイトを使っていますが、特に深い理由があったわけではなく、サイトが見やすくて、使い始めたらそのまま使い続けている、という感じです。
普段、Amazonや楽天で買い物をするような感覚で、本当に気軽にできますよ。
ステップ①:まずはサイトに登録!自分の寄付上限額を調べよう
まずは、ふるさと納税サイトに登録し、自分がいくらまで寄付できるのか、「寄付上限額」の目安をシミュレーションで調べてみましょう。
サイトには簡単なシミュレーターがあるので、源泉徴収票などを見ながら入力すれば、すぐに目安額が分かります。
ここで一つ、私なりのポイントがあります。それは、「算出された限度額いっぱいを、無理に狙わない」ということです。 シミュレーションで出た金額は、あくまでその時点での「上限」です。年末の収入が少し変動したりすると、上限額が変わってしまう可能性もゼロではありません。
私の場合は、算出された上限額ピッタリではなく、そこから数千円引いた、少し余裕のある金額を年間の寄付の目安にしています。
年の初めから中頃までは大まかに寄付をしておいて、収入が確定してくる年末に、残りの枠で数千円程度の寄付をして調整する、というやり方がおすすめです。 そうすることで、「気づいたら上限を超えていて、2,000円以上の自己負担が増えてしまった!」という事態を防ぐことができ、安心してふるさと納税を楽しむことができますよ。
ステップ②:欲しい返礼品を選んで、寄付を申し込む
自分の上限額が分かったら、あとは好きな返礼品を選ぶだけ! 私の場合は「日用品」ですが、もちろんお肉やお魚、果物など、見ているだけでも楽しいですよね。欲しいものが見つかったら、ネットショッピングと同じように申し込み手続きに進みます。
ふるさと納税の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までです。年末は駆け込みで申し込みが殺到したり、決済方法によっては年内扱いにならなかったりすることもあるので、少し余裕を持って申し込むのが良いかもしれません。
ステップ③:「ワンストップ特例制度」を申請して、手間なく完了!
会社員の方にぜひ使ってほしいのが、この「ワンストップ特例制度」です。 これを使えば、面倒な確定申告をする必要がありません。 寄付を申し込む際に「ワンストップ特例を希望する」にチェックを入れ、後日送られてくる書類に少し記入をして、マイナンバーカードのコピーなどを添付して返送するだけ。
最近では、さとふるのアプリを使えば、書類の郵送さえ不要で、スマホだけで申請が完了してしまいます。 これだけで、翌年の住民税が自動的に安くなるなんて、本当に楽で魅力的な制度ですよね。
(注意点として) 医療費控除などで別途ご自身で確定申告をする予定がある場合は、このワンストップ特例制度は使えず、確定申告でふるさと納税の分も申請する必要があるので、そこだけは注意してくださいね。
どうでしょうか? 思っていたより、ずっと簡単だと思いませんか? あとは、返礼品が届くのを楽しみに待つだけです!
始める前に知っておきたい!唯一のデメリット

この「日用品特化」戦略には、一つだけ避けては通れない注意点があります。
それは、「在庫の保管スペース問題」です。
ご想像の通り、トイレットペーパー、キッチンペーパー、ティッシュは、それぞれかなり大きい段ボール箱で一度にドカンと届きます。そのため、それらを収納しておくための、ある程度のスペース(押し入れやクローゼット、納戸など)が必須になります。
我が家では、ウォークインクローゼットの上部の棚に、この3つの段ボールを収納しています。 実は、私が毎年同じ返礼品を選んでいるのには理由があります。
初めて頼んだこの3つの商品の段ボール箱が、たまたまその棚に「シンデレラフィット」したんです! それ以来、下手に他の商品に変えて「サイズが合わなくて入らない…」という事態を避けるため、この組み合わせをリピートし続けています。
もし、お家の収納スペースにあまり余裕がない場合は、返礼品を選ぶ際に、商品の大きさをある程度、事前に確認する必要があるかもしれません。
まとめ:ふるさと納税は、日々の暮らしを楽にする「よりみち」
今回は、我が家が実践している「日用品特化」という、ちょっと変わったふるさと納税の活用術についてお話ししてきました。
私がこの方法を続けている一番の理由は、「買い物の手間が減ることで、時間と心の余裕が生まれる」からです。 トイレットペーパー、ティッシュ、キッチンペーパー。これらは絶対に使うものですが、意外とかさばるし、「あ、ストックがない!」と考えること自体が、地味なストレスになっていました。 その「考えるコスト」から解放されるのは、精神的に本当に大きいんです。
もちろん、実質2,000円の自己負担で、これらの必需品が家に届くというお得さも、大きな魅力の一つです。
「ふるさと納税は、なんだか難しそう」と敬遠していた方でも、この記事を読んで、「これならできるかも」と思っていただけたら嬉しいです。豪華なグルメ品を選ぶのも楽しいですが、日々の暮らしを楽にしてくれる「日用品」という選択肢も、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
あなたの生活に合った、賢いふるさと納税の「よりみち」を見つけてみてください。
以上、ごんでした。



